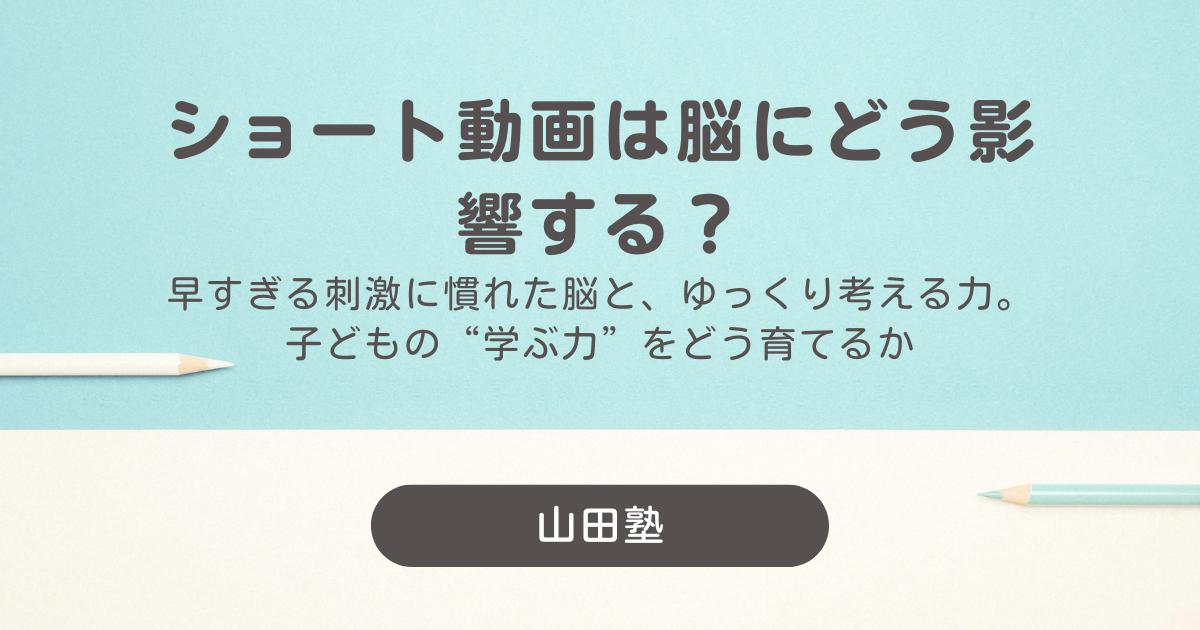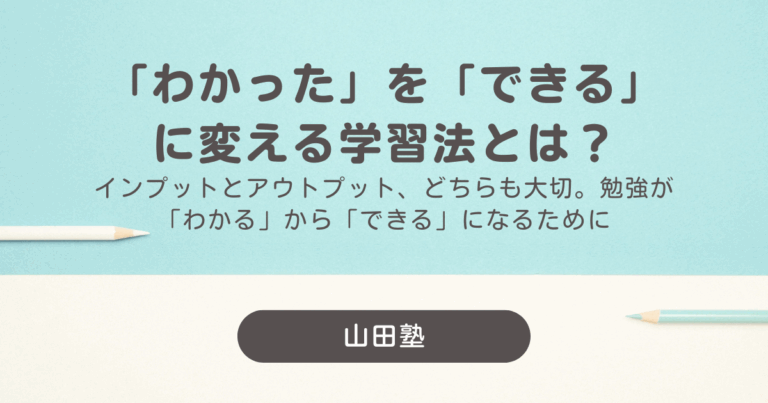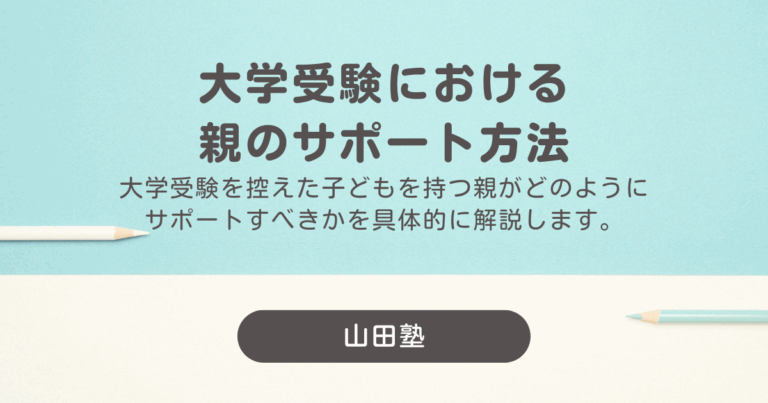「短い動画ばかり見て、勉強に集中できない」「スマホを手放せず、気がつけば何時間も…」——そんな声を、保護者の方からよく聞くようになりました。
TikTokやYouTube Shorts、Instagramリールなどの“ショート動画”は、いまやSNSの中で日常的に流れてきます。
ほんの数秒で笑いや驚きを得られる、強い刺激とテンポの速さが魅力のコンテンツです。
でも実は、こうしたショート動画に限らず、SNSそのものが「脳の報酬系」を強く刺激する設計になっていることをご存じでしょうか?
情報が次々にスクロールされる仕組み、予測できない刺激、突然届く「いいね」やコメント——これらはすべて、脳にドーパミンを繰り返し分泌させ、強い依存を生み出す要因になっています。
特に脳がまだ発達途中にある子どもたちは、このような刺激に対して自制する力が弱く、長時間の視聴やスクロールを止められないまま、学習や睡眠に支障をきたすケースも少なくありません。
本記事では、ショート動画やSNSが子どもの脳にどのような影響を与えるのかを脳科学の視点から解説しながら、家庭でどのように関わっていけばよいかを一緒に考えていきます。
いま、子どもたちの身の回りには「強い刺激」が溢れています。ショート動画はその代表的なものです。
わずか数秒の映像の中に、音楽、セリフ、視覚効果が詰め込まれ、次から次へと終わりなく流れてきます。これらは、脳の「報酬系」と呼ばれる領域を強く刺激し、ドーパミンという快楽物質を何度も放出させます。
このような仕組みは、ギャンブルやアルコール依存とも似た構造を持ち、「もっと見たい」という欲求を自動的に引き起こします。
特にショート動画やSNSが危険なのは、①スマホが常に身近にあり、②制限なく視聴できて、③罪悪感がほとんどないという特徴がある点です。
これは、大人でもコントロールが難しい仕組みです。ましてや、脳が発達途中にある子どもにとっては、なおさら強烈な影響を及ぼしかねません。
実際、前頭前野と呼ばれる「判断力」や「注意力」「感情のコントロール」を担う脳の部位は、思春期を通して徐々に発達していくと言われています。
この時期に強い刺激を長時間浴び続けることは、脳の成長そのものに悪影響を与える可能性があります。
認知心理学の研究では、「短く浅い情報に慣れた脳」は、「ゆっくり考える力」や「集中を持続させる力」が育ちにくいことが指摘されています。
つまり、単なる“スマホの使いすぎ”ではなく、学習や自己制御の土台に深く関わる問題なのです。
もちろん、ショート動画やSNSそのものが悪いわけではありません。内容によっては、子どもの興味や好奇心を引き出すきっかけになることもあります。
しかし、問題は「量」と「コントロール」です。自分の意思では止められないまま見続けてしまうことが、依存の入り口になります。
子どもたちに必要なのは、「ダメだからやめなさい」と一方的に言われることではなく、今の情報環境がどうなっていて、自分の脳がどう反応しているのかを知ること。
そして、安心できる生活環境の中で、集中力や学びの力を少しずつ取り戻していけることだと、僕は考えています。
子どもに見られる変化(集中力の低下、学習意欲の減退など)
「勉強を始めてもスマホが気になってすぐ手が止まってしまう」
「読書やノートまとめができなくなった」
「説明されても内容が頭に入らない」
こうした変化に心当たりがあるご家庭も少なくないはずです。
ショート動画やSNSに長時間さらされた脳は、常に「次の刺激」を求める状態になります。
勉強や読書のように、「時間がかかる」「すぐには成果が出ない」活動が、以前よりも苦痛に感じられるようになるのです。
さらに、音や映像といった強い刺激に慣れた脳は、日常生活の感覚刺激では満足しづらくなり、感情が不安定になったり、無気力になったりすることもあります。
思春期の子どもにとって、これは心のバランスや自己肯定感にも影響を及ぼす可能性があります。
僕たち大人がこうした変化に気づいたときに大切なのは、まず「責めないこと」です。
なぜ集中できないのか、なぜやる気が出ないのか——その背景には、脳の反応や情報環境という“構造的な要因”があるからです。
子ども自身も、「どうしてこんなに気が散るんだろう」と感じながら、コントロールできずに悩んでいるかもしれません。
だからこそ、大人がまずその状況を理解し、少しずつでも改善できるように環境を整えていく必要があります。
脳を守り、学びを支える家庭での工夫
「スマホをやめなさい」と言っても、続かない。
「時間を決めよう」と言っても、すぐに元通りになってしまう——そんな経験はないでしょうか。
実は、スマホやショート動画そのものが悪なのではなく、それ以上に「現実の生活が満たされていない」ことが依存につながっていることが多いのです。
子どもにとって、スマホよりも楽しいこと、落ち着ける場所、認められている感覚が家庭の中にあるかどうかが、依存を防ぐ最大のポイントになります。
以下の3つは、山田塾でもご家庭におすすめしている“根っこを整える工夫”です。
①「目的のない時間」を一緒に過ごす
スマホに頼りたくなる背景には、「一人きりの時間が不安」「静けさに耐えられない」といった感情が隠れていることがあります。
テレビもスマホも消して、会話がなくても、ただ一緒に同じ空間で過ごす。そんな時間が、子どもにとって深い安心感につながります。
② 五感を使った“本物の体験”を増やす
手を使って料理する、自然の中を歩く、読んだ本について話す——こうした体験は、動画では得られない「実感」を子どもに与えます。
脳は、ゆっくりした刺激にも本来喜びを感じるようにつくられています。
③ 成果ではなく、過程を認める
勉強や習い事など、結果が出なければ意味がないと感じてしまいがちな今の子どもたち。
でも、「面白かったね」「ここまで頑張ったね」という声かけこそが、自分の努力を認められたという実感になり、次の学びへの原動力になります。
僕が本当にお伝えしたいのは、「スマホを遠ざけること」よりも、「スマホよりも魅力的な日常」を家庭の中につくっていくことです。
子どもが「ここにいていいんだ」と安心できる時間と空間があること——それが、脳と心を守り、学ぶ力を取り戻すいちばんの土台になると感じています。
山田塾の教育観・姿勢・信念を、あたたかく、誠実に表現
今の子どもたちは、生まれたときからスマートフォンや動画が身近にある情報環境で育っています。
親世代とはまったく異なる世界で、日々、強い刺激や膨大な情報にさらされながら生きています。
だからこそ、これからの時代を生きるためには、「情報を自分で見極め、自分なりの考えを持つ力」がより一層求められます。
SNSやネットの情報には、正しいものもあればそうでないものもあります。何を信じ、どう判断するのか。その軸を育てることが、将来の学びや人生の選択に深く関わってくるのです。
山田塾では、点数や成績だけを追いかけるのではなく、「なぜ学ぶのか」「どう活かすのか」と問いを立てる力、自分の頭で考える習慣を大切にしています。
外からの刺激に流されやすい時代だからこそ、「集中する力」「切り替える力」を自然と身につけられるよう、日々の声かけや授業設計にも工夫を重ねています。
僕が目指しているのは、変化の激しい社会の中でも、自分の価値観を持って学び続けていける子どもを育てること。
そのために、ご家庭と協力しながら、子どもたち一人ひとりに丁寧に寄り添っていきたいと考えています。
まとめ
ショート動画やSNSは、子どもにとって楽しく、日常に根付いた存在です。
しかしその裏側には、脳の成長や学びに影響を与えるリスクもあります。
大切なのは、単に動画を遠ざけることではなく、子どもが安心して過ごせる環境、豊かさを感じられる日常をつくること。
その積み重ねが、集中力や意欲を取り戻し、学ぶ力の土台となっていきます。
僕たち大人ができるのは、今の情報環境を正しく理解し、子どもが本来の力を取り戻せるよう、あたたかく見守ることだと思っています。